
兵庫県伊丹市で小学5年の男児(10)が7月29日に、川沿いにある山道に友達と一緒にヘビを捕まえに行き、その時に捕まえたヘビに午前10時半頃に左手の人さし指を咬まれ、午後1時頃に友達の家で捕まえたヘビをリュックサックから取り出そうとした時に、今度は右手首を咬まれてしまいました。
そのヘビが、「ヤマカガシ」だったので一時は意識不明の状態に…
ヤマカガシは知らずに手を出すと、国内でもトップクラスの危険生物なのです!!
ヤマカガシはどんな毒蛇
1972年に中学生が咬まれて死亡する事故が起きるまで、無毒と思われていました。国内での死亡例は、現在までに4件でとどまっています。
ちなみに、子供頃は「ヤマカカシ」だと思っていました…
◆ 生息地域:北海道と沖縄以外
◆ 生息場所:カエルが好きなので、田んぼ、畑、河川、渓流、池などの水辺近くが多いです。しかし、都心部などの公園などにも生息していたりもしますので、身近な所に住む毒蛇です。
◆ 体長:70~150㎝
◆ 色: 首元が黄色くて、赤と黒のチェック柄が一般的なのである意味では毒蛇カラーなのですが、自分も含めて好きな人には興味をそそる彩りとも言えます。ただし、地域固体によって模様や柄や色が違うのではっきりとこれっ!!と説明しにくいです。兵庫県伊丹市で起きた事故のヤマカガシは、赤系の色が少なく柄も薄くはっきりしないタイプでした。パッと見は、アオダイショウに見えるかもしれないほどです。
◆ 毒:出血毒
◆性格:おとなしく、臆病なので基本的には、見かけるとすぐに急いで逃げてしまうほどです。
じゃあなんで咬まれたの?
となりますが、踏みつけられたり、今回の事故ように捕まえられると防衛本能から咬みついてくるので注意が必要です。
普通毒蛇と聞くと、前歯2本が鋭い毒牙になっているイメージですが、ヤマカガシは上顎の奥歯(2㎜ほど)から毒を発するので浅く咬まれる程度では、毒は入りません。また、一度咬んだだけでは毒が出ないことすらあります。
ここまでの限りだと、危険生物とは程遠いように思えますよね。
恐ろしいのは「毒性」

毒蛇と言えば本州なら「マムシ」で、沖縄なら「ハブ」のイメージが強いかもしれません。
あまり話題にならないので目だっていませんが、ヤマカガシを加えた3種類が日本に生息する陸の毒蛇となっています。
毒蛇の毒の種類は基本的に大きく分けると、「出血毒」と「神経毒」の2種類あります。
厳密には、毒蛇は両方の性質を持ち合わせているのですが、割合が大きい方がどちらに分類されるかで変わってきます。
ヤマカガシの毒の特性
プロトロンビンという血液凝固因子を活性化させます。
そのため、血管内に微小な凝固を発生させて凝固因子をたくさん消費させるので、血を止めたくても固めるものが足りなくなってしまうのです。
しかし、細胞を破壊していくのではないので、痛みもかゆみも感じません。
そのため、血液の作用を狂わせてく「溶血毒」とも呼ばれる少し特殊タイプです。
なので、いつの間にかどんどん身体の中を巡っていってしまいます。
ヤマカガシは、咬むことでだけでなく首の付け根の頚腺という所からも別の成分の毒を飛ばすこともできます。
数時間から1日経ってから、身体の内部での出血が起こり、皮下出血、内臓出血、脳内出血になる可能性があります。
また、凝固因子が活発化することで、血栓ができて腎臓が詰まり急性腎不全を起こして死亡するケースもあります。
子供の場合は、血液の循環が大人よりも早いのでもっと早く症状が出始めます。
咬む以外にも毒がある
蛇と言えば牙から毒が出るのが普通ですが、ヤマカガシはなんと別の所からも毒を出すことができます。
それが、首の後ろです。
ここにも、毒腺を持っていて犬などに襲われた時に首の後ろ、ちょうど頭の付け根の辺りから白い毒液をだして身を守るのです。
なので、牙からの毒とは成分が別のもので、自分が食べたヒキガエルの持っている毒を再利用して使っています。
毒性としては神経毒で、成分はブフォトキシンです。
皮膚にこの毒液が付くと、炎症を起こしてしまいます。
もし、口に入ると下痢やおう吐などを引き起こすのです。
さらに、目に入ると激しい痛みに襲われるほどの力があります。
日本の代表的な毒蛇とは
毎年約3000件の被害があり、10人ほどの方が亡くなっています。
日本で代表的な危険生物と知られている、強力な毒蛇です。
◆ 生息地域: 沖縄県以外は全て
◆ 生息場所: 草むらや落ち葉の下、岩の間、森林など半日陰を好みます。
◆ 体長: 40~100㎝ 顔が三角形なのが特徴で、胴体もスリムな丸型ではなく少し潰れた丸型のような形なので太く見えます。
◆ 色:主に茶色で、赤っぽい「赤マムシ」もいます。模様は、メガネ模様が並んでいるような特有の柄です。
◆ 毒:出血毒ですが、ヤマカガシとは逆に血液凝固を妨げる細胞破壊型です。
◆ 性格: 熱感知で獲物を捕らえるため、人間でも感知したら攻撃してくることがあります。近づいても逃げずに攻撃態勢に入ってくるのですが、一度離れてしばらくすると姿を消しています。夏から秋にかけての繁殖期は、積極的に動くので注意してください。

被害がひどいイメージですが、ここ10年ほどは被害が減り、年間100人ほどの被害にとどまり亡くなる方はいなくなりました。
一言にはハブと言っても、「ホンハブ」「サキシマハブ」「ヒメハブ」「タイワンハブ」の4種類ほどいます。
それぞれ毒の強さも違い、ホンハブは一番毒性が強いため地元のオジーから、昔はハブに咬まれたらすぐに咬まれた所を噛みちぎって捨てていたと、ワイルドな処置をしていたのを聞いた事があります。
◆ 生息地域:沖縄県、奄美諸島
◆ 生息場所:森の木の上や石垣の間など
◆ 体長:種類で大きさが違います。小さい「ヒメハブ」で30~50㎝。「ホンハブ」は100~150㎝で250㎝のものも発見されています。顔がマムシと同様に三角形のような形です。
◆ 色:茶色や黄色に近い色に、茶色の縞模様があるのが4種類とも似た特徴です。
◆ 毒:出血毒でマムシと同じ毒性です。ただ、サキシマハブとヒメハブは毒が弱く、ホンハブとタイワンハブは毒が強いです。
◆ 性格:気が荒く、攻撃的です。全長の三分の二の距離をジャンプして飛びかかってくるので、近づくのは大変危険な好戦的な毒蛇です。
ハブ、マムシ、ヤマカガシではどれが一番毒が強いのか!!
もし、咬まれたら!?
ハブ、マムシ、ヤマカガシではどれが一番毒が強いのか!!
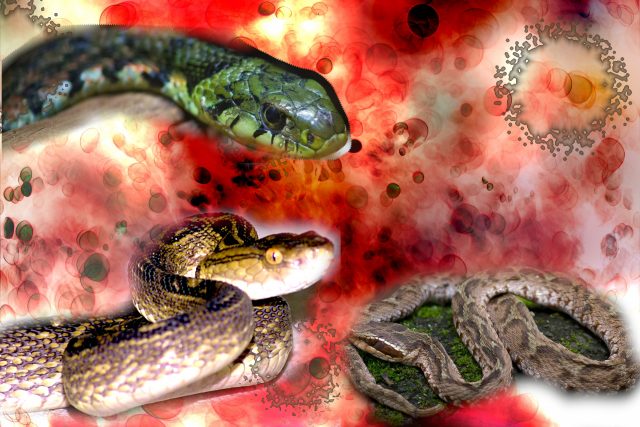
ヤマカガシの毒はハブやマムシと同じ、「出血毒」なのですがその強さは強烈で、ハブの10倍で、マムシの3倍もあります。
ヤマカガシが断トツの一位獲得です!!
しかし、被害の件数はマムシの方が多いです。
それぞれの性質が違う点や全体的な蛇の数、そして毒液の量の違いなどがあるで、毒性に関してだけは国内最強だと言えますが、性格はおとなしいと言うギャップがあるわけです。
ヤマカガシもあまり知られていないので、そうした点では注意が必要だと思います。
ヤマカガシにもし咬まれたら
すぐに、毒をつまみ出す事です。
可能なら、ポイズンリムーバー(注射器のような形の専用の毒吸いだし機)を使用します。
これを一つ持っていると、蜂に刺された時などにも役にたつ優れものですよ。
くれぐれも、口では吸わないでください。
微量でも飲み込む事になりますし、口の中の傷口などから入り込んで行くので逆に悪化します。
処置は早い方がいいですが、激しくするのは危険なので、無理にせかして心拍数が上がらないようにしましょう。
心拍数が早くなれば、それだけ毒が身体全体に早く広まっていく事になるからです。
すぐに即死になる毒では無いのですが、軽く見て処置が遅れないようにしつつも、逆に慌て過ぎて血流を早めて毒が身体全体に流れ込んでいかないように意識して、病院で診てもらいましょう。
ただ、マムシやハブは腫れるのですぐにわかるのですが、ヤマカガシは痛みもかゆみもないので判断しにくいうえに、本当にヤマカガシなのかすらわからない場合もあるでしょう。
しかし、咬まれて毒が入っている場合は血尿や血便、皮下出血の症状がでるのでその時は迷わずに、すぐに病院に行きましょう。
自分で捕まえて飼育したくても…
一般的に遭遇するのは、シマヘビやアオダイショウが多いですが無毒なヘビです。
しかし、知識がないと区別がつかないのでむやみに捕まえようとするのは大変危険です。
例えば、キノコも正しい知識がないとなんでもかんでも取って帰って食べると命にかかわりますよね。
ペットショップなどで手に入れたヘビを、飼いきれずに捨てられている可能性もないとは言い切れないので、どんなヘビかわからないはっきりとわからない時は近づかないのが一番の安全策になります。
特にヤマカガシやマムシやハブなどは、許可なく飼育することは違法になるので違う意味でも注意しなければなりません。
どうしても飼育したい時は、ちゃんとした知識をもって区別できるようになってから捕獲しましょう。
ペットショップで相談して購入を検討してみるのもいいと思いますよ。
ただ、責任をもって最後までお世話してあげましょうね。
ペットショップのヘビは、個人的には見ているだけでも楽しいでおススメですよぉ。
こんな面白いヘビもいたりしますから。
![]()
一瞬ヘビに見えませんでした!?
サボテンなんですけどね(笑)


















コメント